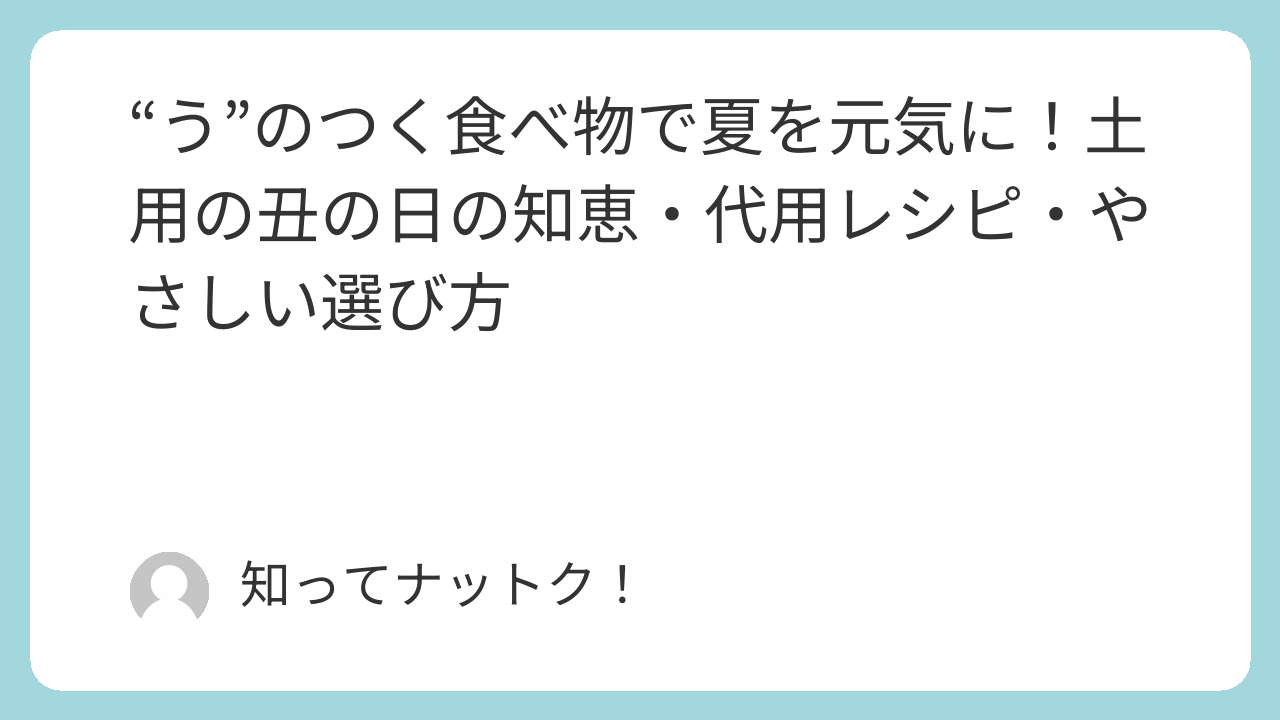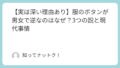土用の丑の日といえば「うなぎ」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実は“う”のつく食べ物全般に意味があるってご存じでしたか?
この記事では、「うなぎ」だけにとらわれない土用の丑の日の過ごし方をご紹介します。
本来の意味や由来から、夏を乗り切る知恵、代わりに楽しめる“う”のつく食材、そして環境にもやさしい工夫まで、やさしく解説しています。

食べ方や楽しみ方に正解はありません。忙しい毎日の中でも、自分に合ったスタイルで季節を楽しむヒントを見つけてみませんか?
スキマ時間で読める内容なので、気軽にチェックしてみてください。
- 土用の丑の日ってどんな日?意味と由来をわかりやすく解説
- 2025年の土用の丑の日はいつ?今年のカレンダーと干支でチェック
- なぜうなぎを食べるようになったの?歴史と由来に迫る
- 地域によって違う!土用の丑の日のユニークな風習
- 「うなぎ以外」でも大丈夫!夏バテ対策になる“う”のつく食材
- スーパーやコンビニでも手軽に買える!“う”のつくおすすめ商品
- 子どもや高齢者にもやさしい!“う”のつく健康食材&簡単レシピ
- 環境にやさしい選択も!代替うなぎのアイデアいろいろ
- 「うなぎを食べない」選択もあり?多様な価値観に寄り添う過ごし方
- SNSで話題!#土用の丑の日みんなの楽しみ方アイデア
- 知っておきたい!土用の丑の日にまつわる雑学・豆知識
- 未来のうなぎを守るために、私たちにできること
- まとめ|今年の土用の丑の日は、自分らしく・心地よく楽しもう
土用の丑の日ってどんな日?意味と由来をわかりやすく解説
「土用」と「丑」の本来の意味とは?
「土用の丑の日」という言葉は聞き慣れていても、それぞれの言葉の意味までは知らないという方も多いかもしれません。
「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前、約18日間のことを指していて、実は年に4回ある季節の変わり目です。
一方「丑の日」は、十二支で数える日付の1つで、12日周期で巡ってきます。
つまり、「土用の丑の日」とは、季節の節目である土用の期間に訪れる「丑」の日という意味になります。
特に夏の土用の丑の日が注目されるようになったのは、夏の厳しい暑さと関係があります。

体調を崩しやすい時期に、しっかり栄養をとって夏を乗り切ろうという昔からの知恵が根づいているんです。
どうして夏に注目されるの?時期の背景
先ほどの通り、「土用の丑の日」は年に複数ありますが、なぜか夏だけが有名ですよね。
これは、夏の土用が梅雨明け直後~真夏にかけての一番暑い時期にあたるためです。
昔の人々にとって、夏の暑さは命に関わるほど深刻な問題でした。
そのため、体力をつけることや、食を通じて健康を保つことがとても大切にされていたんです。

特に丑の日には、「う」のつく食べ物を食べると良いとされ、うなぎだけでなく、うどんや梅干しなども取り入れられてきました。
夏の丑の日が定着した背景には、自然の流れに寄り添う暮らしの知恵が込められています。
2025年の土用の丑の日はいつ?今年のカレンダーと干支でチェック
今年の「土用」と「丑の日」を一覧で確認
土用の丑の日は毎年日付が変わるため、「今年はいつだっけ?」と迷う方も多いですよね。
これは、土用の期間と十二支の「丑」が重なる日を基準にしているためです。
2025年の夏の土用の期間は、7月19日(土)から8月6日(水)まで。
この期間中に訪れる「丑の日」は、
/
・第1回:7月24日(木)
・第2回:8月5日(火)
\
の2回あります。
年によっては、丑の日が1回だけの年もあれば、2025年のように2回ある年もあります。
このような年は「一の丑」「二の丑」と呼ばれることもあります。
2回ある年の過ごし方とおすすめアイデア
丑の日が2回ある年は、どう過ごすのがいいのか悩みがちです。
どちらか一方でしっかり楽しむのも良いですし、それぞれ違ったテーマで過ごすのもおすすめです。

たとえば、1回目は定番のうなぎを楽しみ、2回目は代替食や“う”のつく食材を使った軽めの献立で工夫してみると、変化があって飽きずに楽しめます。
また、家族や友人と一緒にテーマを決めて、「う」のつく食材を持ち寄るイベントのようにしてみるのも、ちょっとした季節の楽しみになりますよ。
何より大切なのは、「無理せず、自分なりのスタイルで取り入れること」。
2025年の丑の日も、自分らしい過ごし方を見つけてみてくださいね。
なぜうなぎを食べるようになったの?歴史と由来に迫る
平賀源内が仕掛けた“夏の販促術”とは
うなぎを土用の丑の日に食べるようになったきっかけには、江戸時代の有名な学者・平賀源内のエピソードが関係しています。
このアイデアが話題となり、結果的にうなぎの売れ行きが伸びたことから、丑の日=うなぎというイメージが広がっていったと伝えられています。
うなぎは昔の夏バテ防止フードだった?
当時の人々にとって、うなぎは滋養がある食べ物という認識がありました。
暑さで食欲が落ちたり体力を消耗しがちな夏に、栄養のある食材を意識して取り入れるという考えは、今よりもっと身近だったかもしれません。
特に、うなぎはたんぱく質や脂質が豊富で、当時の食生活では貴重な栄養源のひとつだったようです。
その意味でも、丑の日にうなぎを食べる習慣は理にかなっていたともいえます。
かば焼きという調理法の知恵と工夫
現在よく知られている「うなぎのかば焼き」は、香ばしく焼いた香りと甘辛いタレの味わいが特徴ですよね。

この調理法も、うなぎ独特の風味や骨の多さを和らげ、食べやすくするための工夫だったと言われています。
表面を香ばしく焼き上げることで、クセを抑えつつ美味しく仕上げられるようになり、当時の人たちの知恵が感じられる一品となりました。
こうした背景から、「丑の日にうなぎ」は文化として受け継がれるようになっていったのです。
地域によって違う!土用の丑の日のユニークな風習
しじみ汁や“うし肉(牛肉)”を食べる地域も
土用の丑の日といえば「うなぎ」というイメージが強いですが、地域によっては違う食べ物を取り入れているところもあります。
たとえば、島根県や鳥取県では「しじみ汁」を飲む習慣があると言われています。
しじみはミネラルが豊富で、夏の暑さで失いやすい栄養素を補う食材として親しまれてきました。
また、関西地方の一部では「うし肉=牛肉」を食べるという風習もあるようです。

「丑の日」にかけて“うし”を食べることで縁起を担ぐ、という考え方ですね。
このように、地域ごとの食文化が反映された風習には、その土地の暮らしや自然環境が深く関係しています。
“う”のつく食べ物で願掛け?日本独自の言霊文化
「うなぎ」や「うし肉」に限らず、土用の丑の日には「う」のつく食べ物を選ぶことが縁起が良いとされています。
これは、日本独自の“言霊(ことだま)”の考え方が背景にあります。
言葉に宿る力を大切にしてきた日本では、「“う”の音を取り入れると運気が上がる」といった考え方が古くから存在していたようです。
そのため、うなぎが手に入らない場合や苦手な場合でも、うどんや梅干しなど「う」のつく食材で代用することも立派な風習のひとつ。
土用の丑の日は、自分に合った「う」の食べ物を楽しむというスタイルが今では広がっています。
「うなぎ以外」でも大丈夫!夏バテ対策になる“う”のつく食材
うどん|冷温どちらも楽しめる万能食
「う」のつく代表的な食材のひとつが「うどん」です。
さっぱりと冷たくしても、温かくしても食べられるうどんは、季節や体調に合わせてアレンジしやすいのが魅力です。
特に暑い日は冷やしうどんに薬味をのせたり、胃腸が疲れているときには、優しい温うどんでリラックスした食事にするのもおすすめです。
うめ|疲労回復にぴったりの酸味食材
梅干しも「う」のつく伝統的な食材として人気があります。
酸味が食欲をそそり、夏の暑さで食が進まないときにも取り入れやすい食材です。
ごはんのお供にするだけでなく、冷たいお茶に少し加えて梅茶にしたり、おにぎりにして持ち運ぶのも便利で実用的です。
うずらの卵|栄養豊富で見た目もかわいく
お弁当などにもよく使われる「うずらの卵」も、土用の丑の日にぴったりの“う”食材です。
サイズが小さいので子どもでも食べやすく、ゆで卵やフライ、スープの具としても活躍してくれます。
見た目もかわいらしく、食卓に取り入れるだけで気分が明るくなるような一品です。
市販の“う”食材(ふりかけ、ゼリーなど)
忙しいときや手軽に済ませたい日には、市販の「う」のつく商品を活用するのもひとつの方法です。
たとえば「うめ味」のふりかけや「うんしゅうみかんゼリー」など、商品名や味付けに“う”がつくアイテムを意識して選んでみるだけでも、ちょっとした季節のイベント気分が楽しめます。
日々の中に無理なく取り入れられる「う」のつく食材で、気軽に土用の丑の日を楽しんでみてくださいね。
スーパーやコンビニでも手軽に買える!“う”のつくおすすめ商品
コンビニで揃う“う”メニューとは?
忙しい日や仕事帰りなどに便利なのが、コンビニで見つかる“う”のつく食材やメニューです。
たとえば、うめ風味のおにぎりや、うどん入りのカップ麺、うずらの卵入りサラダなど、探してみると意外と多くの商品に“う”が使われています。
冷たい麺類やスープ系のお惣菜も充実していて、暑い日でも無理なく食事が楽しめるのが嬉しいポイントです。
コンビニを上手に活用すれば、調理の手間を省きながら、気軽に土用の丑の日の雰囲気を取り入れることができます。
スーパーで買える調理不要アイテムも便利
スーパーには、家庭で手軽に楽しめる“う”のつく商品が豊富にそろっています。
たとえば、うなぎ風味のかば焼き風お惣菜や、うどんの冷凍・チルド商品、梅干し入りの混ぜごはんの素など、火を使わずに済む便利なアイテムがたくさん見つかります。
また、カット野菜と組み合わせて作れるうずら卵のサラダセットや、お弁当にそのまま使えるうめ味のおかずもおすすめです。
「ちょっと取り入れてみようかな」という気軽な気持ちで、スーパーやコンビニをのぞいてみるだけでも、土用の丑の日の楽しみ方が広がるかもしれません。
子どもや高齢者にもやさしい!“う”のつく健康食材&簡単レシピ
アレルギー・減塩・食べやすさを考慮した例
土用の丑の日は家族みんなで楽しみたいイベントですが、体調や年齢に応じた食材選びも大切です。
たとえば、塩分を控えたい高齢の方には、減塩タイプのうめふりかけや、だしで風味をつけた優しい味わいのうどんがおすすめです。
アレルギーを気にされる場合は、原材料表示をよく確認しながら、シンプルな素材の市販品や、家で味付けを調整できるメニューを選ぶと安心です。
家族みんなで楽しめる夏の献立アイデア
子どもにも食べやすいのが「うずらの卵入りサラダ」や「梅しそ風味の混ぜごはん」など、見た目も味もやさしいメニューです。
おにぎりやそうめん、野菜スティックなどと組み合わせれば、調理の負担も少なく、さっぱりとした夏の献立が完成します。
“う”のつく食材を取り入れることで、無理なく土用の丑の日の雰囲気を味わえますし、食卓に季節感もプラスされます。
手軽でやさしい工夫をしながら、家族みんなが笑顔になれるような一日にしたいですね。
環境にやさしい選択も!代替うなぎのアイデアいろいろ
ナスの蒲焼き風アレンジレシピ
うなぎの代わりに、植物性の食材を使った「蒲焼き風」レシピも人気が高まっています。
中でもおすすめなのが「ナス」を使ったアレンジです。

縦に切ったナスを焼き、うなぎのたれ風の味付けをするだけで、見た目も食感も蒲焼きらしく仕上がります。
皮の香ばしさと甘辛い味が絶妙で、ごはんとの相性も抜群です。
うなぎを控えたいときの代替メニューとして、手軽に楽しめる一品です。
豆腐・大豆ミートで代用できる商品や工夫
最近では、大豆ミートや豆腐を使った“うなぎ風”の商品も増えています。
蒲焼き風に味付けされた冷凍食品やレトルト商品もあり、火を使わずに調理できるものも多いので、手間なく楽しめるのが魅力です。
また、自宅で豆腐をしっかり水切りして焼き、甘辛いタレをからめれば、手作りの蒲焼き風メニューも作れます。
動物性食品を避けたい方や、環境への配慮を意識する方にとっても、こうした代替食は無理なく取り入れやすい選択肢となっています。
「うなぎを食べない」選択もあり?多様な価値観に寄り添う過ごし方
環境保護の視点から食べない人が増えている
近年では、うなぎの資源問題や環境への影響を考えて、土用の丑の日にあえてうなぎを食べないという選択をする人も増えています。
ニホンウナギは絶滅危惧種に指定されていて、乱獲や生息地の減少などが問題視されています。
こうした背景から、持続可能な食文化への関心が高まり、「食べる・食べない」を自分で選ぶスタイルが広がっています。
文化は大切。でも「自由な選択」も尊重される時代
うなぎを食べることは、もちろん日本の文化のひとつとして今も大切にされています。
ただし、それを必ず守らなければいけないというものではなく、現代では一人ひとりが自分に合った過ごし方を選べる時代です。

大切なのは、伝統を知ったうえで「どう楽しむか」を自分で選ぶこと。
うなぎを食べる日というよりも、「自分や家族の健康を考える日」として向き合うのも、今の時代に合った柔軟な楽しみ方かもしれません。
選択肢の多様さが認められる今だからこそ、それぞれの想いに寄り添った土用の丑の日の過ごし方を考えてみてはいかがでしょうか。
SNSで話題!#土用の丑の日みんなの楽しみ方アイデア
手作り蒲焼きや“推しのう”レシピがバズ中
最近では、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSでも、土用の丑の日にちなんだ投稿が注目を集めています。
特に人気なのが、「手作りの蒲焼き風レシピ」や「“う”のつく食材で作るアレンジ料理」の投稿です。

ナスや豆腐を使った代替うなぎ、うどんのアレンジレシピなど、見た目も楽しくて工夫が光るメニューがたくさんシェアされています。
写真付きで紹介されているものが多く、見ているだけでもアイデアが広がります。
X(旧Twitter)やInstagramで見つけたリアルな投稿
SNSでは「#土用の丑の日」や「#うのつく食べ物」などのハッシュタグを使って、ユーザーが自分の楽しみ方を共有しています。
「今年は豆腐蒲焼きに挑戦しました」や「家族で“う”のつく料理を持ち寄りしました」といったリアルな投稿には、共感の声も多く寄せられていて、気軽に真似できる内容が多いのも特徴です。
忙しい中でも楽しめる工夫や、子どもと一緒に作った簡単メニューなど、生活に密着したヒントがたくさん詰まっています。
気になるキーワードで検索してみると、あなたにぴったりのアイデアが見つかるかもしれません。
知っておきたい!土用の丑の日にまつわる雑学・豆知識
昔は「うなぎ」以外にも●●を食べていた?
現在ではうなぎが定番のイメージですが、実は昔はうなぎ以外の食材も幅広く食べられていたことがわかっています。
江戸時代以前には、地域や家庭ごとに「“う”のつくものならOK」とされ、うどんや梅干し、瓜(うり)なども定番の一品でした。
当時は保存性や入手しやすさも大切なポイントだったため、身近な“う”の食材を工夫して取り入れるのが一般的だったようです。
“う”のつく言葉が縁起物とされたワケ
日本には古くから「言霊(ことだま)」という考え方があり、言葉には特別な力が宿るとされてきました。
丑の日に「“う”のつく食べ物を食べると元気になる」と信じられていたのも、こうした文化の影響です。

“う”の音には、力強さや運を引き寄せるイメージが重ねられ、夏の体調管理だけでなく、願掛けや厄除けの意味でも大切にされていたと考えられています。
現代でも、こうした背景を知ることで、より意味を感じながら土用の丑の日を楽しむことができそうですね。
未来のうなぎを守るために、私たちにできること
食べる頻度や量を見直してみる
うなぎを楽しむこと自体は文化の一部として大切ですが、これからの時代は「どのように楽しむか」がより問われていくかもしれません。
たとえば、毎年必ず大量に食べるのではなく、回数や量を少し見直してみることもひとつの方法です。
希少な食材であることを意識しながら、感謝の気持ちを持っていただくことで、より意味のある食体験にもつながります。
持続可能な養殖うなぎを選ぶという選択肢
うなぎの中には、環境や資源に配慮した方法で育てられた「持続可能な養殖うなぎ」もあります。
一部のスーパーや専門店では、そうした背景を明記して販売されていることもあり、商品を選ぶ際の基準としてチェックしてみるのもおすすめです。
自分の選択が、未来のうなぎや環境を守る一歩になるかもしれません。
無理のない範囲で、できることから始めてみるという姿勢が、これからの土用の丑の日の過ごし方として求められているのではないでしょうか。
まとめ|今年の土用の丑の日は、自分らしく・心地よく楽しもう
土用の丑の日は、うなぎを食べるだけの日ではなく、古くからの季節の知恵や風習が詰まった日本文化のひとつです。
本来の意味や由来を知ったうえで、自分に合った過ごし方を見つけることが、現代の楽しみ方につながります。
「う」のつく食べ物を取り入れる工夫や、地域ごとの風習を参考にするのも良いですし、環境に配慮した代替メニューを選ぶのも、立派な選択のひとつです。
SNSや市販の商品を活用すれば、忙しい中でも無理なく雰囲気を味わうことができます。
無理に伝統にこだわる必要はなく、今年の丑の日は、自分らしく、心地よく過ごしてみてはいかがでしょうか。