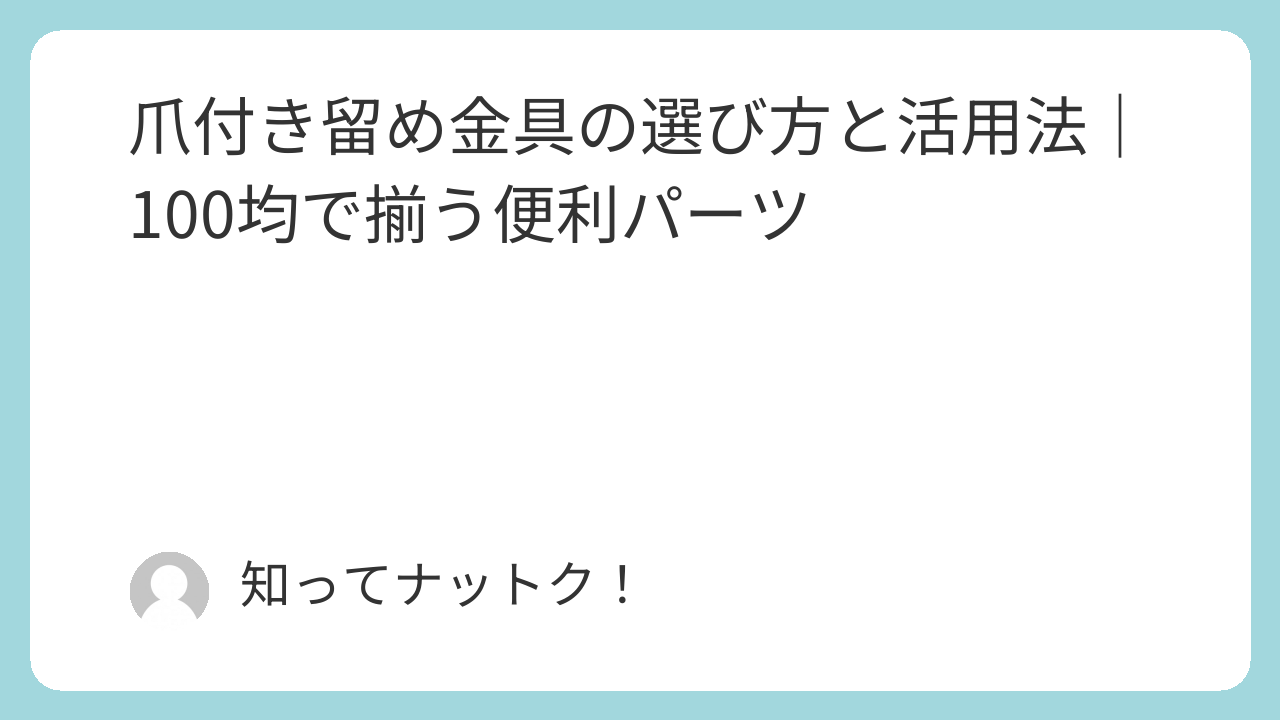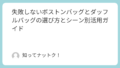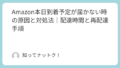爪付き留め金具は、アクセサリーや小物作りでよく使われるパーツです。
しかし「どこに売っているのか」「サイズはどう選べばいいのか」と迷う人も少なくありません。

この記事では、100均で探せる売り場の目安や、カラーやサイズ選びのコツを整理しました。
また、初心者でも取り入れやすい基本の使い方や、ネックレスやチャームなどへの応用アイデアも紹介します。
さらに、似ている金具との違いや、よくある失敗の防ぎ方もあわせて解説します。
用途に合わせた代替パーツの例も取り上げているので、手に入らないときの参考にもなります。
「探す・選ぶ・使う・応用する」を順に整理しているため、必要な情報をすぐにチェックできます。
ハンドメイドを気軽に始めたい方や、パーツ選びで迷いやすい方に役立つ内容です。
アマゾンや楽天にも色々な種類が揃っているので使いやすいものが購入出来ますよ♪
▼爪付き留め金具▼
爪付き留め金具とは?初心者向けの基本知識
爪付き留め金具を見かけても「どんなときに使うの?」と感じる人は少なくありません。

まずは基本的な特徴や用途を整理して、全体像をイメージしてみましょう。
どんな用途に使えるパーツか
爪付き留め金具は、小さな金具の一種で、主に布やレザー、紐状の素材をしっかり固定するために使われます。
アクセサリー作りやチャームの制作、キーホルダーのパーツ固定などに利用されることが多く、100円ショップや手芸用品店で広く取り扱われています。
一般的な特徴と便利な点
一般的に爪付き留め金具は以下のような特徴を持っています。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 形状 | 小さな金属パーツで、両端に爪がついている |
| 用途 | 紐や布端を挟んで留める |
| 利点 | 接着剤なしでも固定しやすい/手軽に扱える |
| 入手しやすさ | 100円ショップや手芸コーナーなどで購入可能 |
このように、特殊な道具がなくても利用できることが多いため、初心者でも扱いやすい点が魅力です。
ただし製品ごとにサイズや強度は異なるため、実際のパッケージ表示や説明を確認して用途に合うかどうかを見極める必要があります。
100均で手に入る!爪付き留め金具の売り場案内
どこに行けば手に入るのかが分からないと探すのに時間がかかります。

そこで、ここでは100円ショップでの代表的な売り場の傾向を紹介します。
ダイソーで探せる主なコーナー
ダイソーでは、爪付き留め金具は主に手芸用品コーナーやアクセサリーパーツ売り場に置かれていることが多いです。
レジン用パーツやビーズと並んで陳列されるケースもあり、アクセサリー作り向けの商品群の中に含まれていると探しやすくなります。
また一部の店舗では、工作関連やクラフトコーナーにまとめて置かれていることもあります。
セリアで見つかる定番の場所
セリアでも基本的にはハンドメイドコーナーが中心です。
特にアクセサリーパーツやビーズと一緒に並んでいるケースが多く、ディスプレイが小分けされているため比較的探しやすい傾向があります。
一部の店舗ではレジン用品コーナーに含まれている場合もあるため、複数の関連売り場をチェックすると見つけやすくなります。
| 店舗 | 主な売り場 | 補足 |
|---|---|---|
| ダイソー | 手芸用品コーナー/アクセサリーパーツ売り場 | レジンやビーズと一緒に並ぶこともある |
| セリア | ハンドメイドコーナー/レジン用品コーナー | 小分けディスプレイで探しやすい場合が多い |
このように、店舗によって売り場の表記や配置が異なるため、1つのコーナーだけで見つからない場合は「手芸」「クラフト」「レジン」関連の棚を順に確認すると効率的です。
カラーやサイズの選び方のコツ
色やサイズが豊富にあるからこそ、選び方に迷いやすいパーツです。

基準を押さえておくと、自分の目的に合った金具を見つけやすくなります。
人気のカラーバリエーション
爪付き留め金具には、シルバー・ゴールド・アンティーク調など、複数のカラー展開が見られます。
シルバーはすっきりとした印象で、シンプルなデザインに馴染みやすいのが特徴です。
ゴールドは華やかさをプラスしやすく、アクセントに取り入れられることが多いです。
アンティーク調や黒系のカラーは落ち着いた雰囲気を演出できるため、シックなデザインに向いています。
サイズ選びで注意したいポイント
サイズを選ぶときは、取り付ける素材の太さや幅とのバランスを確認することが大切です。
事前に紐や布端の幅を測っておき、金具の内径と合うかどうかをチェックして選ぶと安心です。
素材や強度もチェックしておきたい点
カラーやサイズだけでなく、素材や厚みも重要な要素です。
真鍮や鉄製など金属の種類によって強度が異なり、軽いもの向けか、やや重さのあるアイテムにも使えるかが変わります。
また、メッキ加工の有無によって耐久性や見た目の印象も変わるため、長く使いたい場合は仕上げの違いも確認すると良いでしょう。
| 項目 | 選び方のポイント |
|---|---|
| カラー | シルバー=シンプル/ゴールド=華やか/アンティーク=落ち着き |
| サイズ | 取り付け素材の幅や太さに合うか確認 |
| 素材 | 金属の種類や加工の有無で強度や雰囲気が変わる |
このようにカラー・サイズ・素材の3点を総合的に見ることで、用途に合う爪付き留め金具を選びやすくなります。
爪付き留め金具が便利とされる理由
数ある金具の中でも爪付き留め金具がよく使われる理由があります。

その便利さを知っておくと、用途に合うかどうか判断しやすくなります。
工具を使わず簡単に扱える点
爪付き留め金具は、爪の部分を曲げて素材を挟み込むだけで固定できる仕組みです。
専門的な工具を必ずしも必要とせず、平たいもので軽く押さえるだけでも留められることがあります。
そのため、初心者でも比較的取り入れやすく、ちょっとした工作やハンドメイドに利用しやすいのが特徴です。
100均で揃えやすいコスト面の魅力
多くの100円ショップでは、数個入りや小分けパックで販売されているため、試しやすい価格帯で購入できます。
初めて使う人でも気軽に手に取りやすく、必要な分だけを選べるのも利点です。
コストを抑えながらアクセサリーパーツを揃えられるため、練習や試作の段階でも利用しやすい存在といえます。
| 便利な理由 | 内容 |
|---|---|
| 工具不要 | 爪を折り曲げるだけで素材を挟んで固定できる |
| 低コスト | 100円ショップで手軽に購入でき、試しやすい |
| 扱いやすさ | 初心者でも取り入れやすく、練習用にも向いている |
このように、「手軽さ」と「入手しやすさ」が爪付き留め金具の大きな魅力といえます。
初心者でもできる!基本の使い方ステップ解説
実際にどうやって使えばいいのかを知ると、一気にハードルが下がります。

基本のステップを押さえて、安心して取り付け作業を進めていきましょう。
準備に必要なもの
爪付き留め金具を使う際には、まず取り付けたい素材と金具を用意します。
必要に応じて平ペンチやピンセットなどの道具があると作業がスムーズになります。ただし簡単な場合は爪を指で軽く折り曲げるだけでも使えるため、必須ではありません。
4ステップで進める取り付け方法
以下は一般的な取り付け手順の一例です。
| ステップ | 作業内容 |
|---|---|
| 1 | 紐や布端など、取り付けたい素材を用意する |
| 2 | 金具の中央に素材を差し込み、位置を合わせる |
| 3 | 爪を内側に折り曲げて、素材を挟み込む |
| 4 | 軽く押さえて固定し、外れないか確認する |
これらのステップを踏むことで、特別な技術がなくても安定して取り付けられます。
仕上がりをきれいにするコツ
仕上げの段階で爪の折り曲げ具合を均等にすることが見た目を整えるポイントです。
このように準備~固定~仕上げを順番に確認して進めれば、初心者でも落ち着いて作業を進めやすくなります。
似ている金具との違いを確認しよう
見た目が似ている金具は多く、間違えて選んでしまうこともあります。

違いを知っておくと、用途に合わせた選択がスムーズになります。
カニカンや丸カンとの違い
カニカンは小さなフック状の金具で、チェーンやパーツ同士を着脱可能にするために使われます。
丸カンはリング状で、パーツとパーツをつなげる役割を持っています。
これらはいずれも「つなぐ」ためのパーツであるのに対し、爪付き留め金具は素材の端を固定する役割を担っています。
目的が異なるため、用途に合わせて使い分ける必要があります。
ヒートンとの使い分けポイント
ヒートンは先端に小さなリングがついたネジ状の金具で、レジンや木材にねじ込んで固定し、吊り下げパーツを取り付けるために利用されます。
爪付き留め金具は挟み込んで固定するのに対し、ヒートンは差し込んで固定する仕組みです。
素材や作りたいアイテムによって、どちらが適しているかが変わってきます。
| 金具の種類 | 主な役割 | 固定方法 |
|---|---|---|
| 爪付き留め金具 | 素材の端を挟んで固定する | 爪を折り曲げて挟み込む |
| カニカン | チェーンやパーツを着脱可能にする | フックを開閉して接続 |
| 丸カン | パーツ同士をつなぐ | リングを開いて通し、閉じる |
| ヒートン | レジンや木材にねじ込んで吊り下げる | ネジのように差し込み固定 |
このように、見た目が似ていても「固定する」か「つなぐ」かなど役割は大きく異なります。

それぞれの特徴を理解しておくことで、用途に応じた正しい金具を選びやすくなります。
よくある失敗と対処方法
金具が外れやすいときの工夫
小さな金具でも扱い方を誤ると外れやすくなることがあります。 爪をしっかり折り曲げないと、金具が緩んで外れてしまうことがあります。
よくあるケースと、その回避のための工夫を確認しておきましょう。 この場合は爪を均等に内側へ曲げることが重要です。
また、柔らかい素材の場合は金具の内側に布や紙を少し挟むと、摩擦が増えて安定しやすくなります。
サイズが合わなかった場合の対応
素材に対して金具が大きすぎると固定力が弱まり、小さすぎると素材が入らないことがあります。

このような場合はサイズを測ってから選び直すのが基本です。
もし手元にある金具がやや大きい場合には、余った部分を折り返して厚みを持たせるなど、調整しながら使う方法もあります。
逆に小さい場合は無理に押し込まず、適切なサイズの金具を改めて用意する方が仕上がりが安定します。
| よくある失敗 | 原因 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 金具が外れやすい | 爪の固定が不十分/素材が滑りやすい | 爪を均等に曲げる/摩擦を増やす工夫をする |
| サイズが合わない | 金具と素材の幅や太さが不一致 | サイズを測り直す/余裕を作るか適切なサイズを選ぶ |
このように、失敗の多くは固定不足かサイズ不一致に起因します。
事前に素材の幅を測り、丁寧に爪を閉じることで多くのトラブルは避けやすくなります。
アクセサリーやチャームに応用できる活用アイデア
基本の使い方を覚えたら、アクセサリーやチャームへの応用も楽しめます。

シンプルなアイテムに少し工夫を加えるだけでアレンジの幅が広がります。
ネックレスの留め具に取り入れる方法
細めの紐やチェーンを使ったネックレスは、端をそのままにしておくとほつれやすくなります。
爪付き留め金具を利用すれば端をすっきり処理しつつ、金具を接続するパーツとしても活用できます。
その先にカニカンや丸カンをつなげることで、着脱可能な留め具を簡単に作ることが可能です。
デザインに合わせて金具のカラーを選べば、見た目の印象も整いやすくなります。
キーホルダーやバッグチャームへの応用
爪付き留め金具は布や革紐を使ったキーホルダーやチャームにも応用できます。
例えば革ひもや布テープを端で留めてから金具を取り付ければ、バッグチャームやストラップにアレンジできます。
シンプルな素材に組み合わせるだけでもオリジナリティが出やすく、ハンドメイド感を楽しみやすいのも魅力です。
| アイテム | 活用方法 | ポイント |
|---|---|---|
| ネックレス | 紐やチェーンの端を固定して留め具として使う | カラーをデザインに合わせる |
| キーホルダー | 革ひもや布を固定し、金具を接続パーツにする | 耐久性を考えたサイズ選びをする |
| バッグチャーム | 布やリボンをまとめて留めて装飾に活用 | 色味を揃えると統一感が出る |
このように、爪付き留め金具は固定と装飾の両方に役立つパーツとして応用範囲が広いのが特徴です。
爪付き留め金具の代わりになるアイテム
もし爪付き留め金具が手に入らないときや合わないときには代替策もあります。

他のアイテムと比較して、自分の目的に近いものを選びましょう。
カニカンや丸カンで代用するケース
爪付き留め金具がない場合、カニカンや丸カンを使って素材同士をつなぐ方法があります。
カニカンは開閉式なので、アクセサリーの着脱部分として利用できます。
丸カンはシンプルにリング状のパーツをつなぐだけで使えるため、固定ではなく接続を目的とする場面で有効です。
レジンやヒートンとの組み合わせ
布や紐ではなく、樹脂や小物を使いたい場合にはレジンとヒートンの組み合わせが有効です。
レジンでパーツを固め、その中にヒートンを差し込むことで吊り下げられる状態にできます。
これは爪で挟むのではなく、素材そのものにねじ込んで固定する仕組みのため、より強度が必要なアイテムにも使いやすい方法です。
| アイテム | 使い方 | 特徴 |
|---|---|---|
| カニカン | 紐やチェーンに取り付けて接続部に使う | 開閉式で着脱が可能 |
| 丸カン | パーツ同士をリング状でつなぐ | シンプルな接続に適している |
| ヒートン+レジン | 樹脂や木材にねじ込んで吊り下げ用にする | 固定力を高めたいときに便利 |
このように、爪付き留め金具がなくても代わりになるパーツを選択することで制作を進められるケースがあります。
用途や素材の種類に合わせて、最適な代替アイテムを検討すると安心です。
初心者から寄せられる質問と回答(FAQ)
初めての人が気になりやすいポイントは共通しています。
よくある質問を整理しておくと、迷ったときに確認しやすくなります。
耐久性はどのくらいある?
爪付き留め金具の耐久性は、素材やサイズ、使用環境によって異なります。
長く使いたい場合は、実際の商品パッケージや素材表示を確認してから選ぶと安心です。
重いものを付けても大丈夫?
爪付き留め金具は基本的に軽量な布や紐、リボン類を留めるのに適したパーツです。
重量のあるアイテムに使用すると外れやすくなる可能性があるため、強度を必要とする場合は別の金具や方法を検討した方が安全です。
どんな工具と一緒に使うと便利?
必ずしも専用の工具は必要ありませんが、平ペンチやラジオペンチを用意しておくと作業がしやすくなります。
特に爪をしっかりと折り曲げたいときや、仕上がりをきれいに整えたいときに便利です。
また、ペンチの先に布を当てて使うと金具に傷がつきにくくなるという工夫もあります。
| 質問 | ポイント |
|---|---|
| 耐久性はある? | 軽量な小物向け、重い物には不向きな場合も |
| 重いものに使える? | 基本的に軽い素材用、強度が必要な場合は別パーツ推奨 |
| 必要な工具は? | ペンチがあると便利だが必須ではない |
このように「耐久性」「用途の範囲」「補助工具」といった観点を押さえておくことで、初めてでも迷いを減らしやすくなります。
まとめ|100均金具で広がるハンドメイドの楽しみ
記事の要点
- 爪付き留め金具は、紐や布端を爪で挟んで固定するための小さなパーツ
- 100均では手芸用品コーナーやアクセサリーパーツ売り場に置かれていることが多い
- カラー・サイズ・素材を比較しながら選ぶと用途に合いやすい
- 基本の4ステップで取り付けができ、初心者でも扱いやすい
- カニカン・丸カン・ヒートンなど似た金具との違いを理解して選ぶのがポイント
- よくある失敗は「固定不足」と「サイズ不一致」なので、事前に素材幅を確認する
- ネックレスやチャームなどアクセサリー作りにも応用できる
- 代替パーツを組み合わせれば用途の幅が広がる
- FAQでは「耐久性」「重さへの対応」「工具の有無」などが初心者の疑問として多い
あとがき
爪付き留め金具は、小さな部品ながら工夫次第で多彩な使い道が広がるパーツです。
100均でも手に入るため、試しやすさやコスト面での安心感も魅力のひとつです。
本記事では「探し方」「選び方」「使い方」「応用方法」を一通り整理しました。

必要な場面に合わせて参考にしていただければ、ハンドメイドの幅をより自由に広げられるはずです。
身近なパーツをきっかけに、新しいアイデアを楽しむ時間としてご活用ください。