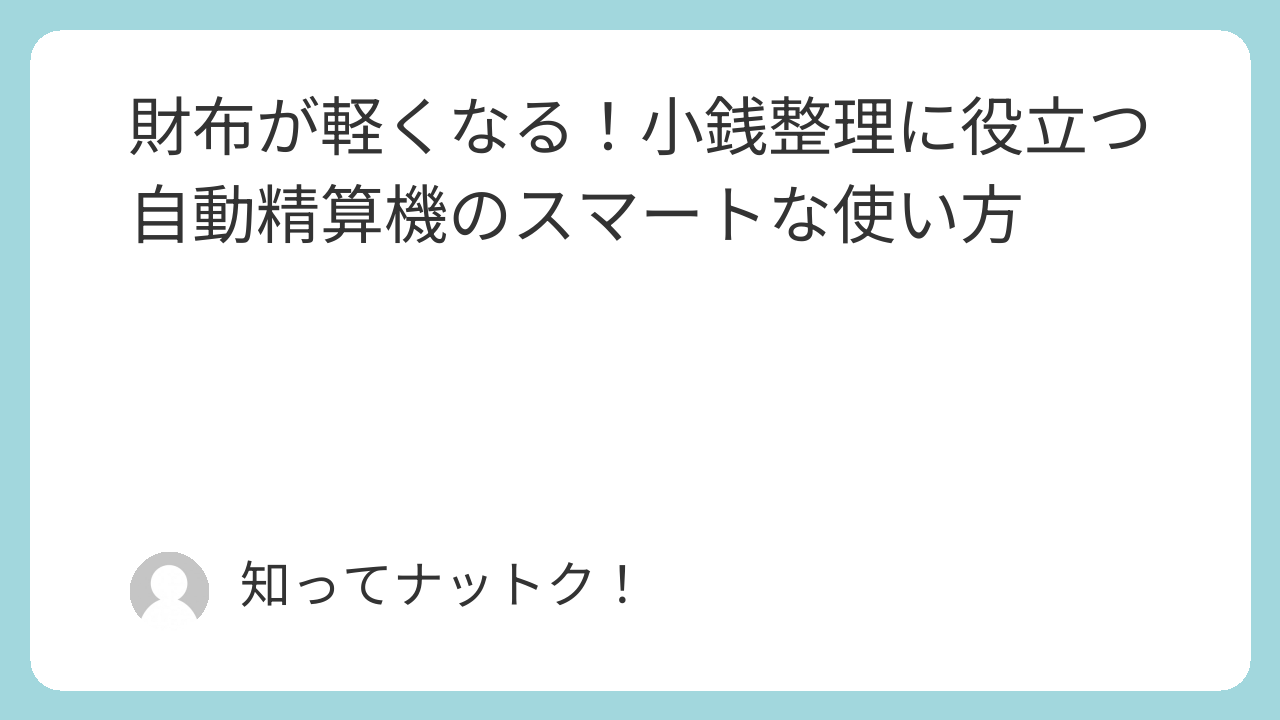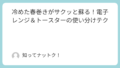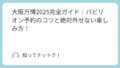財布の中にたまった小銭、ついつい後回しにしていませんか?
気づけばパンパンに膨れ上がった財布に、ちょっとしたストレスを感じることもあるはず。

そんな小銭をスマートに処理できる方法のひとつが「自動精算機の活用」です。
でも、便利な反面、ルールやマナーを守らないと周囲に迷惑をかけてしまうことも…。
この記事では、自動精算機を使って小銭を上手に整理するコツと、トラブルを防ぐためのポイントをわかりやすくご紹介します。
小さな習慣を変えるだけで、財布も気持ちもスッキリ!今日からできる小銭整理、始めてみませんか?
貯まった小銭は自動精算機でかしこく使う
小銭の「処理」に悩んでいる方にぴったりなのが、自動精算機を活用する方法です。

今では、銀行で小銭を両替するのにも手数料がかかる時代。
以前のようにATMに少しずつ預け入れることも難しくなり、小銭をどう扱うか悩む方も少なくないのではないでしょうか。
そんな時におすすめなのが「自動精算機での支払い」です。
10円玉や50円玉、100円玉なら自動販売機で使うこともできますが、自動精算機なら1円玉や5円玉まで活用できるのが嬉しいポイント。

いつの間にか財布の中で増えてしまった小銭も、スムーズに消費することができます。
ただし、自動精算機で小銭を使うときには、ルールやマナーを守ることが大切です。
これから小銭を上手に使いたいと考えている方は、ぜひこの点を意識してみてください。
周囲に迷惑をかけず、ルールを守って使おう
自動精算機を使って貯まった小銭を賢く処理するのは、今の時代、とても合理的な方法と言えます。
もちろん、銀行やATMで手数料を支払ってまとめる方法もありますが、できるなら無駄な費用はかけたくないもの。
自動精算機での支払いなら、少額でもお会計の足しになりますし、手数料もかかりません。

きちんとルールを守れば、
これほど効率的な方法はないかも♪
私自身もこの方法で小銭を減らしていますが、やり方を間違えると周りの人に迷惑をかけてしまうこともあるので、特に注意しています。
ここからは、私が普段気を付けているポイントを交えながら、自動精算機で小銭を使う際の注意点をご紹介します。
少しずつコツコツ。枚数制限を守って使おう
小銭を使うときには「枚数制限」があることを覚えておきましょう。
法律では、同じ種類の硬貨は一度に20枚までと決まっていて、21枚以上を受け取るかどうかはお店の判断に委ねられています。
※お店側がOKすれば、それ以上でも会計できることもあります
自動精算機でも、基本的に「20枚以内」といったルールが設けられていることが多く、大量に投入すると故障の原因になってしまうことも。
決められた枚数を超えて使おうとするのは、単なる迷惑行為になってしまいますので、必ずルールを守ることが大切です。

私も一度も枚数制限を破ったことはありません。このルールだけはしっかり守るようにしています。
また、「同じ硬貨じゃなければたくさん入れてもいいんでしょ?」と思うかもしれませんが、枚数が多すぎると機械に負担がかかるため、種類に関係なく20枚程度にとどめるのがおすすめです。
たとえ家に500枚の1円玉が眠っていたとしても、1回に10枚ずつ使っていけば、必ず使い切ることができます。
私自身も、昔の貯金箱やお店のレジの小銭を整理して、数百枚の1円玉・5円玉・10円玉を少しずつ消費していき、1年ほどでほとんど使い切ることができました。
焦らず、コツコツと使い続ければ、小銭はちゃんと減っていきます。

絶対に一度に100枚もまとめて入れたりせず、必ずお店のルールに従いましょう。
もしルールが書かれていない場合でも、法律上の「20枚以内」を守ることがマナーですよ。
事前に小銭を用意してスムーズに
自動精算機で小銭を使うとき、財布からその場でゴソゴソと取り出していると、後ろのお客さんを待たせてしまい、迷惑をかけてしまいます。
並んでいる人たちも、内心「早くして…」と思っているかもしれませんよね。
だからこそ、スムーズに支払えるよう、事前に準備しておくことがとても大切です。

私の場合、あらかじめその日に使いたい小銭を小さなポーチや袋に分けておきます。
こうしておけば、会計の際にはサッと取り出して、わずか数秒で小銭を精算機に入れることができます。
これなら店員さんにも後ろに並んでいる人にも迷惑をかけずに済み、自分も焦らずに支払いを終えられるので、とてもおすすめです。
その場で財布から1円玉を10枚探すとなると、どうしても時間がかかってしまうし、焦ってしまうものです。
だからこそ、あらかじめしっかり準備しておくことが、小銭をスマートに使うコツですよ。
挿入口が狭いタイプは無理にまとめて入れない
自動精算機にはさまざまなタイプがあり、挿入口が広いものもあれば、自動販売機のように小さな投入口のものもあります。
広い挿入口なら、小銭をまとめて投入しても問題ありません(もちろん、枚数制限を守るのが前提です)。
ただし、狭いタイプの場合は一気に流し込もうとすると詰まってしまうリスクがあるので注意が必要です。
こういった機械では、焦らずに数枚ずつ小銭を入れていきましょう。

あらかじめ小銭を用意しておけば、ゆっくり入れてもそれほど時間はかかりません。
一度に詰まらせてしまうと、トラブルになる恐れがあるので、落ち着いて丁寧に使うようにしましょうね。
変形した硬貨は使わないように
めったにないことですが、もし変形した硬貨を自動精算機に入れてしまうと、正しく読み取れなかったり、機械の故障につながる可能性があります。
そのため、小銭を準備する段階で、変形や損傷している硬貨を見つけた場合は、無理に使わずに別の方法で消費しましょう。
自動精算機はあくまで「正常な状態の硬貨」を前提に作られているので、機械に負担をかけないためにも気を付けたいですね。
キャッシュレス派の場合はどうする?
これまでご紹介してきた方法は、現金払いをする機会がある方向けです。
普段からキャッシュレス決済をメインにしている方は、自動精算機を使う機会自体が少ないかもしれません。
そんな場合でも、例えば10円玉以上の小銭なら、自動販売機でちょっとした飲み物を買うなど、上手に使い切る工夫をしてみましょう。
とはいえ、キャッシュレス中心の生活では、そもそも小銭がたまりにくいので、あまり神経質になる必要はありません。
現金払いが多い方は、自動精算機を上手に利用して、日々の買い物のついでに少しずつ小銭を減らしていくと、財布もスッキリしますよ。
そもそも「小銭が貯まらない習慣」を身につけよう
小銭をスムーズに使う方法を知るのも大切ですが、そもそも小銭が財布にたまらないようにする工夫も、ストレスフリーな生活には欠かせません。
ここでは、日常生活の中で「小銭を増やさない習慣」についてご紹介します。

まず、現金で支払う際は「できるだけピッタリの金額を支払う」意識を持ちましょう。
例えばコンビニで買い物をするとき、細かい小銭を積極的に使っていけば、自然と財布の中に残る小銭は減っていきます。
「あ、今10円玉が3枚あるから、ここで使っちゃおう」と意識するだけでも、小銭の滞留を防ぐことができます。
次に、できるだけ「お札で支払わない」工夫も有効です。
なんとなくお札を出してお釣りを受け取る癖があると、小銭はどんどんたまっていきます。小さな買い物こそ手持ちの小銭を活用することで、自然に財布が軽くなっていきますよ。
また、キャッシュレス決済を取り入れるのも効果的です。
最近は、スマホひとつで支払いが完結する便利なサービスがたくさんあります。小銭を持つ機会自体を減らせるので、無駄なストレスもぐっと減るでしょう。

特に、スーパーやドラッグストアなど、普段使いのお店でキャッシュレスが使える場合は、積極的に活用したいですね。
さらに、「小銭専用のポーチを持つ」のもおすすめです。
財布とは別に小さなポーチを持っておくと、小銭が財布にパンパンにたまる心配がなくなります。
会計のときも、ポーチの中から必要な小銭を出せばスムーズですし、見た目もスマートに支払いができます。
こうした小さな工夫を積み重ねていけば、そもそも小銭に悩まされる場面はぐっと減っていきます。
「貯まった小銭をどう処理するか」だけでなく、「小銭をためない生活スタイル」を目指していくことも、毎日を軽やかにするコツですよ。
まとめ
小銭を貯めすぎない工夫から、自動精算機での正しい使い方まで、意外と知らないポイントはたくさんあります。
ルールとマナーを守ることで、周囲に気を遣うことなくスムーズに小銭を整理できるようになりますよ。
財布の中も心も軽くなる小さな工夫を、ぜひ今日から取り入れてみてください。無理なく続けることで、自然と小銭に悩まされない毎日が手に入ります。

自動精算機を味方につけて、
スマートな小銭ライフを楽しみましょう!