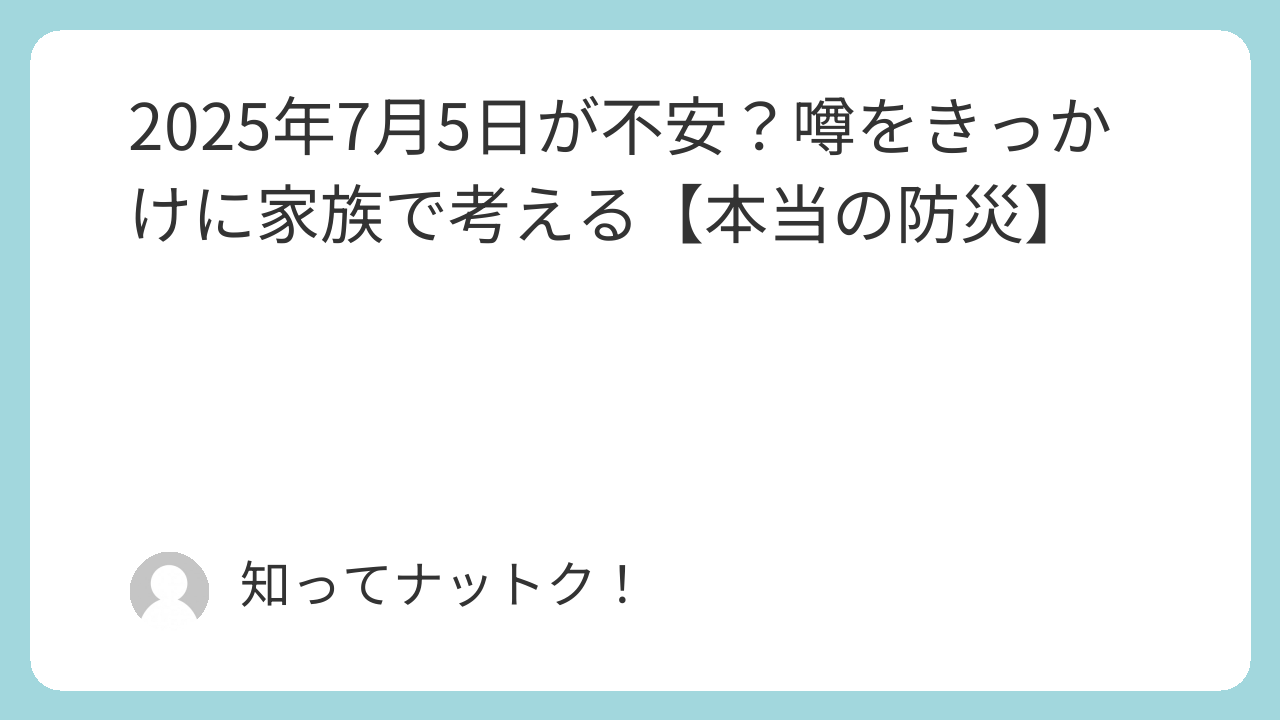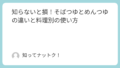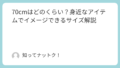「2025年7月5日に大地震が来るらしい」そんな噂がネットで話題になっています。

確かな根拠はなくても
心がざわついてしまうのは自然なこと。
でも大切なのは、不安に流されるのではなく、備えるきっかけに変えることです。
本記事では、デマに振り回されない情報リテラシーのポイントを踏まえつつ、家族でできる防災対策をわかりやすく解説しています。
小さな子どもがいるご家庭や、防災を身近に感じにくい方にも、「これならできそう」と思ってもらえるヒントをたくさん詰め込みました。
話題の「2025年7月5日」に感じる不安
「2025年7月5日大地震説」はどこから来た?
最近SNSを中心に、「2025年7月5日4時18分に大地震が起きる」といった噂が広まっています。
発端はある漫画作品のフィクションですが、一部では“予言”のように捉えられ、不安を抱える人も増えてきました。
なぜ噂が広まりやすいのか?
こうした情報は、確かな根拠がないにもかかわらず、人々の不安を刺激し、拡散されやすい傾向があります。
特に家族を守る立場にある人ほど、「何か準備しておいた方がいいのでは…」と心配になるのも無理はありません。
不安を行動に変えるきっかけに

でも、大切なのは“噂に振り回されること”ではなく、“備えるきっかけにすること”。
この記事では、不確かな情報にどう向き合えばいいのかを整理しながら、家族みんなでできる防災対策について考えていきます。
その情報、本当に信じて大丈夫?
デマと本当の情報の違いを見分ける
災害に関する話題はセンシティブだからこそ、「それって本当?」と一度立ち止まって考える力が求められます。
SNSでの拡散スピードは速く、誰かの投稿があっという間に広まり、多くの人が信じてしまうことも。
でも、根拠のない“っぽい話”と、きちんと検証された“確かな情報”はまったく別もの。
情報の発信源がどこなのか、複数の公的な機関で同じように伝えられているかをチェックするのが基本です。
それが最近、地震などの大規模災害が続いているため世の中の不安感が増してしまい、その不安感がSNSを通じて一気に拡大して、あたかもこの原作が予言書であると捉えてしまう人が増えてしまって、今回の噂となったのだと考えられます。※あくまでも私個人の感想です。
信頼できる情報源ってどこ?
* 気象庁、防災科学技術研究所などの政府機関
* 自治体の公式サイトや広報誌
* NHKなど信頼性の高い報道機関
このような情報は、検証や責任のもとで発信されているため、安心して参考にできます。
一方で、SNSの個人アカウントや「~らしい」という不確かな言い回しは、あくまで補助的な参考程度にとどめるのが無難です。
噂は「備え」のきっかけと考える

「もしかしたら地震が来るかもしれない」という噂を完全に無視するのではなく、「備えるチャンスが来た」と前向きに捉えるのが賢い姿勢です。
大切なのは、感情に流されず、冷静に自分と家族の安全を見直すこと。
「信じる・信じない」ではなく、「備えて損はない」と考えれば、デマもきっかけに変えられます。
家族みんなで考える防災のカタチ
家族構成に合わせた備え方
防災対策は、「家庭ごとに違う」のが前提です。
小さな子どもがいる、ペットがいる、高齢の家族がいるなど、状況に応じて必要な準備も変わってきます。
だからこそ、家族で一緒に話し合って、「わが家に合った備え方」を見つけておくことが大切です。
たとえば、乳幼児がいる家庭では、オムツやミルク、おしりふきなどの備蓄も必要。高齢者がいる場合は、常備薬や介護用品のストックを忘れずに用意しましょう。
避難ルートと連絡手段を共有しよう
災害時は、家族が同じ場所にいないこともあります。
だからこそ、いざというとき「どこで落ち合うか」「どうやって連絡を取るか」を事前に決めておくことが安心につながります。
・災害時伝言ダイヤル(171)やLINE、メールの使い方
・小学生でも理解できるシンプルな避難マップ
日頃からシミュレーションしておくことで、緊急時にも冷静に行動しやすくなります。
子どもと一緒に防災を考える工夫
「こわいから話したくない」ではなく、子どもにもできるだけわかりやすく、防災の大切さを伝えていくことが大切です。
最近では、防災絵本やアニメ、防災カードゲームなど、子ども向けの教材もたくさんあります。
また、家族で一緒に防災グッズをそろえたり、避難訓練をしてみることで、防災が自然と身につく習慣にもなります。

「楽しく・わかりやすく」を意識して、小さなうちから防災の力を育てていきましょう。
子どもに伝えたい「こわくない防災」
怖がらせない声かけ・遊びながら学べる防災
防災の話題はときに重くなりがちですが、子どもに伝えるときは“怖がらせない工夫”が大切です。
「もし地震が来たら、こうやって安全な場所に行こうね」など、できるだけポジティブな言葉を使って説明しましょう。
鬼ごっこやかくれんぼのような遊びの中に「安全な場所に逃げる」動作を取り入れるだけでも、自然と身につきます。ゲーム感覚でできる避難訓練は、特に小さな子どもに効果的です。
絵本・動画・カードゲームなどの活用法
最近では、防災をテーマにした子ども向け絵本やYouTubeの動画、防災カードゲームなど、楽しく学べる教材が増えています。
難しい言葉を使わずに、災害が起きたときの流れや、やるべきことをイメージしやすくなっています。
たとえば、
* 防災の豆知識をクイズ形式で学べるカードゲーム
* 子ども向けアニメの防災シリーズ動画
親子で一緒に読む・観る・遊ぶことで、防災への抵抗感が和らぎ、「自分ごと」として考えるきっかけになります。
学校や保育園と連携しておくべきこと
家庭だけでなく、子どもが長い時間を過ごす学校や保育園との連携も欠かせません。いざというとき、
* 保護者への連絡方法
* 子どもの引き渡しルール
などを、事前に確認しておくと安心です。
また、保育園や学校での避難訓練に関する情報は定期的にチェックしておきましょう。
もし不明な点があれば、先生やスタッフに相談することも大切です。防災は、家庭と施設の“チームプレー”で取り組むもの。普段からのコミュニケーションが、子どもの安全につながります。
実践しやすい!日常に取り入れる防災習慣
防災グッズの見直し(子ども用サイズやアレルギー対応)
いざというときのための防災グッズは、年齢や体調、家族構成に合わせて見直しておくことが大切です。

特に子どもがいる家庭では、成長に応じたサイズの着替えや、好きなお菓子・絵本なども追加しておくと安心感につながります。
また、アレルギーのある方は非常食の成分表示にも要注意。アレルゲンを含まない非常食や、低刺激の衛生用品なども忘れずにチェックしましょう。
「ながら防災」買い物・散歩中でも意識できること
日常のちょっとした行動の中でも、防災を意識することはできます。
たとえば、スーパーやコンビニの近くにある避難場所の場所を確認しておく、道に倒れやすそうな電柱や看板をチェックするなど。
「この道、夜でも明るいかな?」「地震のとき、ここにいたらどう動く?」など、自分の行動範囲に照らして考えておくことで、有事のときの判断力がぐっと高まります。
定期的な家族ミーティングのすすめ
家族全員が集まるタイミングで、「もし地震が起きたらどうする?」を話し合う習慣を持つのも効果的です。
ポイントは、難しく構えず、会話の延長として防災の話題を取り入れること。
* 連絡手段と集合場所の共有
* 非常食の試食や持ち出し袋の中身チェック
月に1回、食卓での「防災ミニトーク」だけでも十分。少しずつ家族の中に防災意識が根づいていきます。
噂より確かな備えを
噂で不安になるより、正しい情報と準備を
「2025年7月5日に地震が起きる」という噂に不安を感じている人は少なくありません。
でも、その不安に飲み込まれてしまうよりも、信頼できる情報をもとに、自分にできる準備を一つずつ進めることが何よりも大切です。
SNSではさまざまな情報が飛び交いますが、まずは自治体や気象庁などの公式発表をチェックし、冷静な判断を心がけましょう。

不安な気持ちは「行動」に変えてこそ、安心につながります。
家族を守れるのは、日々のちょっとした心がけから
防災は特別なことではありません。
今日の買い物のついでに非常食を一つ買い足す、子どもと一緒に避難ルートを歩いてみる、そんな“小さな積み重ね”が、いざというときに家族の命を守る力になります。
噂がきっかけでも構いません。
大切なのは、それをどう活かすか。日常に備えを取り入れることで、情報に流されず、安心して暮らせる力が自然と身についていきます。
まとめ
* 2025年7月5日の噂は、根拠のない情報として広まったもの
* 信頼できる情報源を見極める力(情報リテラシー)が大切
* 家族構成に応じた備えを話し合っておくことが安心につながる
* 子どもには「こわくない防災」を、遊び感覚で伝える工夫を
* 防災グッズは定期的に見直し、日常の中で“ながら防災”を意識
* 不安より行動へ。小さな積み重ねが大きな安心を生む

不確かな情報が広まる時代だからこそ、「正しく知って、やさしく備える」。それが家族を守る、いちばん確かな力だと思います。